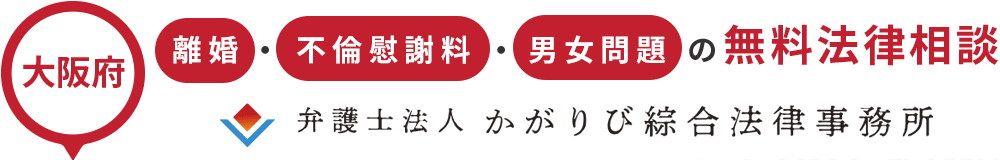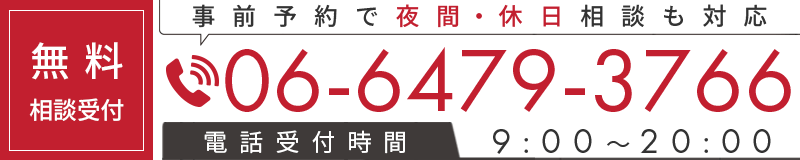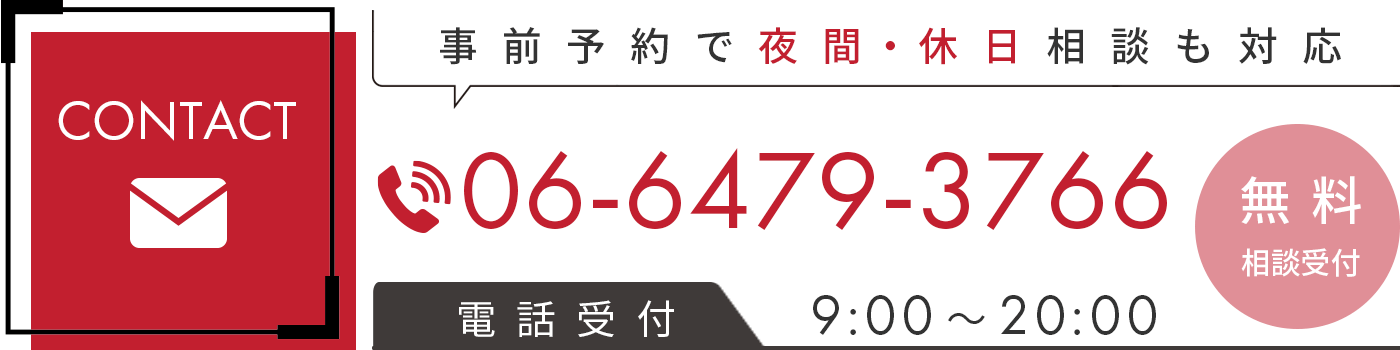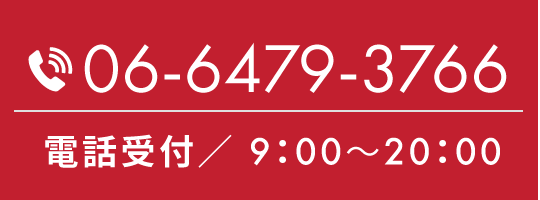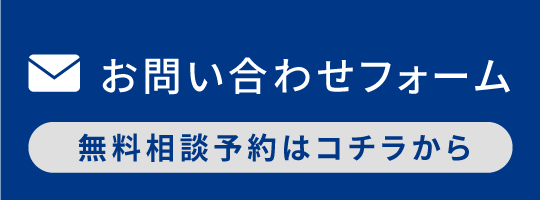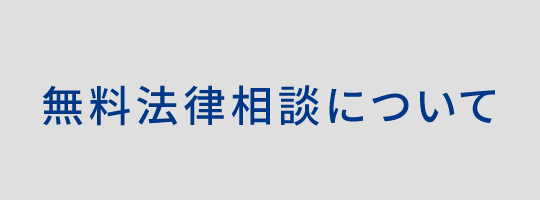親権・面会交流
お子さんとの面会交流は、子育てに関わる親の権利
離婚後、子どもに会わせてもらえない…そんな苦しい状況から抜け出すためにあなたが知るべきこと
「離婚はしたけれど、子どもにだけは会いたい…」
離婚は夫婦関係の終わりを意味しますが、親子の絆が切れることはありません。お子さんにとって、あなたはお子さんを愛し、見守る大切な存在であることに変わりはないのです。
しかし、離婚後に「子どもに会わせてほしい」と願っても、元配偶者から拒否され、会えない日々を送っている方もいらっしゃるかもしれません。
「なぜ、私には会う権利がないのだろう?」 「子どもは、私に会いたがっているだろうか…」
そうした苦悩や不安を抱えているあなたへ。
お子さんとの面会交流は、子育てに関わる親の権利であり、義務です。同時に、親の愛情を受けて育つ、お子さん自身の権利でもあります。そして何よりも、お子さんの利益が最優先されるべきという大原則があります。
この記事では、男女問題に強い弁護士である私が、どのような場合に面会交流が難しくなるのか、そして、お子さんと再会し、その健やかな成長を見守るために、あなたが今できることについて、具体的に解説します。あなたの苦しい状況から抜け出し、お子さんとの温かい関係を再構築するための道筋を示せれば幸いです。
面会交流とは?なぜお子さんにとって重要なのか
面会交流とは、離婚後に子どもと同居しない親(非監護親)が、子どもと会って交流することを指します。子どもと直接会うだけでなく、手紙や電話、プレゼントのやり取りなども面会交流に含まれます。
監護親(子どもと同居している親)と非監護親が不仲である場合、面会交流がスムーズに行われないことは少なくありません。しかし、別居している親と子どもとの円満で継続的な交流は、親子の絆を保つ上で非常に重要です。
- お子さんの安心感:お子さんは、別居している親が自分を見捨てていないことを確信でき、精神的な安定に繋がります。
- 豊かな人格形成:お子さんは、両親からの愛情を等しく受けることで、家族や様々な人との交流を通じて、愛情や信頼の大切さを体験し、豊かな人格を形成することができます。
裁判所の審判例においても、面会交流は「子の監護義務を全うするために親に認められる権利である側面を有する一方、人格の円満な発達に不可欠な両親の愛育の享受を求める子の権利としての性質も有する」と明確に述べられています。つまり、面会交流は、親の権利であると同時に、お子さんの権利でもあるのです。
子どもに会わせてもらえないのはなぜ?面会交流が制限されるケースとは
本来、面会交流を認めるかどうかは、お子さんの心身の状況、監護状況、お子さんの意思や年齢、面会交流がお子さんの監護や教育に与える影響、父母それぞれの意思や葛藤状況などを総合的に判断し、**「お子さんの利益があるか否か」**で検討されます。
夫婦が円満に離婚し、お互いにお子さんの幸せを第一に考えている場合は、積極的に会わせてもらえる可能性が高いでしょう。また、離婚前の調停や裁判で、親権や面会交流に関する取り決めがある場合は、通常その取り決めに従うことが求められます。
それでも、残念ながら、両親の不仲が原因で信頼関係が築けず、面会交流を拒絶されてしまうケースは少なくありません。
面会交流が制限される可能性のあるケース
法的に面会交流が制限される可能性があるのは、以下のような「お子さんの利益を害するおそれがある」と判断される場合です。
- 非監護親による子どもの連れ去りのおそれがある場合
- 非監護親による子どもへの虐待のおそれがある場合
- 非監護親が監護親に対して、または子どもに対して、暴力やモラハラを振るっていた経緯がある場合
- 非監護親が子どもを粗雑に扱ったり、不安定な精神状態にある場合
- 子ども自身が明確に面会交流を拒否している場合(特に年齢が高く、意思を尊重すべき場合)
- 面会交流が、お子さんの監護や教育に悪影響を及ぼすと考えられる場合
しかし、上記のような明確な理由がないにもかかわらず、元配偶者の感情的な理由だけで面会交流を拒絶されてしまうケースも多々あります。このようなトラブルのリスクを減らすためには、元配偶者との交渉を弁護士に依頼し、面会交流の方法について明確なルールを定めておくことを強くおすすめします。
弁護士に依頼する3つの大きなメリット
子どもとの面会交流は、お金に代えられないほどの価値がある、お子さんの大切な問題です。あなたの権利、そしてお子さんの権利を守り、適切な面会交流を実現するために、弁護士のサポートは非常に有効です。
1. 適正な面会交流の方法に取り組んでくれる
面会交流の方法は、お子さんの利益を最も優先して考慮した上で決定しなければなりません(民法766条1項)。監護親が感情的に「面会交流を認めたくない」と考えていても、それがお子さんにとって適切とは限りません。拒否する正当な理由がない限り、非監護親ともきちんと面会交流が行われる方が、お子さんの情操教育の観点からも望ましいと考えられます。
弁護士に依頼することで、法律や過去の裁判例、実務の運用を踏まえ、適正な条件による面会交流を、早期かつ円滑に実現できる可能性が高まります。
また、面会交流のルールを決める際には、以下のような具体的な項目を明確にしておく必要があります。
- 面会交流の日時・頻度
- 面会交流時の宿泊の可否
- 子どもの受け渡し方法
- 監護親などの立会いの有無
- 子どもに対するプレゼントのルール
弁護士は、これらの複雑なルール決めを、あなたの希望を最大限に尊重しつつ、法令や裁判例に基づき、お子さんの利益に合致する形でサポートします。
2. あなたに代わって交渉してくれる
子どもとの面会交流について揉めている状況では、監護親と非監護親の仲が険悪であるケースがほとんどです。そのため、父母間で直接話し合っても、感情的になり、合意に至るのが非常に困難な場合があります。
弁護士を介することで、冷静な話し合いが期待できるほか、あなたが相手と直接顔を合わせる必要がなくなるため、精神的なストレスを大幅に軽減できるでしょう。また、合意した内容を公正証書や調停調書として記録に残すことで、紛失や改ざんを防ぎ、合意内容が明確化されるというメリットもあります。
3. 離婚調停・訴訟、面会交流調停の対応を一任できる
面会交流についての話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の離婚調停、離婚訴訟、あるいは面会交流調停・審判といった法的手続きによって、面会交流の方法を取り決めることになります。
特に離婚に伴う面会交流の場合、面会交流以外の離婚条件(親権、養育費、財産分与など)についても弁護士のサポートが必要となることが多くあります。弁護士に依頼すれば、上記の各法的手続きの対応をすべて一任できるため、複雑で煩雑な手続きに煩わされることなく、スムーズに解決へと進めることができます。
離婚後も、お子さんとの絆を諦めないで
お子さんとの面会交流ができない状況は、親として非常に苦しいものです。しかし、お子さんとの絆は、何ものにも代えがたい宝物です。
感情的な対立で会えないのは、お子さんの健全な成長にとっても大きなマイナスです。お子さんの利益を第一に考え、適切な面会交流を実現するためにも、ぜひ専門家である弁護士の力を借りてください。
私たち、かがりび綜合法律事務所は、男女問題に特化し、お子さんとの面会交流に関する多くのご相談に対応してきました。あなたの状況に寄り添い、お子さんとの大切な時間を守るために、全力でサポートいたします。
一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。 あなたとお子さんの未来のために、私たちがお力になります。
裁判所・調停委員が親権者を決定する際の7つの判断基準【大阪の離婚弁護士が解説】
裁判所・調停委員が親権者を決定する際の7つの判断基準【大阪の離婚弁護士が解説】
大阪のかがりび綜合法律事務所で離婚問題に特化している弁護士の野条です。離婚に際して、お子様の親権についてお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
裁判所や調停委員が親権者を決定する際には、「父母のどちらに引き取られるのが、お子様にとって最も幸せか」を第一に考えて判断します。親権争いを有利に進めるためには、これらの判断基準をしっかりと把握しておくことが重要です。
ここでは、親権獲得に向けて押さえておきたい7つの判断基準について、大阪の離婚問題に強い弁護士が詳しく解説します。
1. お子様への愛情の深さ
親権者を決定するための判断基準の一つは、「お子様にどれだけ愛情を注いでいるか」です。お子様に対してより大きな愛情を持っていると判断された親が、親権獲得において有利になります。
愛情の大きさは、お子様との関わり方、過ごし方、一緒に過ごした時間の長さなどから判断されます。例えば、お子様との時間を優先するために仕事をセーブしたり、お子様を第一に考えて生活してきた経緯があるならば、その愛情の深さが伝わるでしょう。
一般的に、仕事で家を空けることが多く、お子様と過ごす時間が母親よりも短くなりがちな父親にとっては不利になりやすい基準です。親権争いに勝つためには、できるだけお子様と一緒に過ごす機会を増やし、今後も継続して過ごせることを具体的にアピールする必要があります。
ただし、お子様への愛情が評価されれば必ず親権が取れるわけではありません。愛情はあくまで親権者を決める判断基準の一つに過ぎず、他の事情も総合的に考慮して判断されます。
2. 監護実績の有無と今後の養育環境
離婚調停までの「監護実績」も、親権者を判断する上で非常に重要なポイントです。
監護実績とは、これまでお子様とどのように過ごし、どのように世話をしてきたかという子育ての実績を指します。具体的には、以下のような行動が該当します。
- 日々の食事や弁当の準備
- お子様の健康管理
- 入浴、着替え
- 勉強や遊びの付き添い
- 寝かしつけ
- 保育園・幼稚園・習い事などの送り迎え
- 育児休暇の取得
これまでにきちんと子育てを行い、お子様と多くの時間を共有してきた親であれば、今後もこれまでと同じように養育できると判断されやすくなります。これまでの育児経験を具体的にアピールすることが大切です。
なお、小学校・幼稚園・保育園の連絡帳、お子様の監護を行っていることがわかる写真、父母間で行われたお子様の監護に関するやり取りなどが監護実績の証拠となります。供述の裏付けとなるため、あらかじめしっかりと準備しておきましょう。
3. 親の経済状況や健康状態の安定性
親の経済状況や健康状態が安定しているかどうかも、重要な判断基準です。お子様を育てるには多大な費用がかかるため、経済的な余裕がある場合は有利になりやすく、特に相手よりも収入が多い場合はアピールポイントとなるでしょう。
しかし、収入が少ない場合でも、相手からの養育費や財産分与などで養育費をカバーできると判断されることも少なくありません。そのため、収入が少ないからといって親権を諦める必要はありません。
ただし、養育費で仮にお子様の生活費がまかなえても、ご自身の生活資金が確保できず、お子様との生活に支障をきたす恐れがある場合は、親権獲得が難しくなることもあるため注意が必要です。ある程度安定した経済状況がなければ、不利になる可能性があると考えておいた方がよいでしょう。
また、親の健康状態についても、肉体的・精神的に問題があると子育てに支障が出ると判断され、親権の獲得が難しくなることがあります。最低限の子育てが可能であれば親権者になれるケースもありますが、重い病気を患っている場合は注意が必要です。持病があっても問題なく子育てできるのであれば、育児に支障がないことをアピールするために、病院で診断書をもらっておくことをお勧めします。
4. お子様の意思の尊重
裁判所が親権者を決める際は、お子様の意思が尊重されます。特に、お子様の年齢が15歳以上であれば、その意向は非常に重要な判断基準となります。
ケースにもよりますが、例えば母親が父親よりも有利な状況にある場合でも、お子様が父親と暮らしたいと希望すれば、その気持ちが優先されることがあります。親としては、親権を取りたい気持ちがあっても、お子様の意思を尊重することが重要です。
なお、一般的に意思が尊重されるのは15歳以上とされていますが、15歳未満であっても年齢によってはある程度お子様の意思が考慮されます。10歳前後であればすでに意思能力が備わっていると考えられるため、お子様の意思を尊重して親権者を決定するケースも増えています。
5. 複数のお子様がいる場合のきょうだい不分離
親権争いのポイントの一つに「きょうだい不分離の原則」という考え方があります。これは、「お子様が複数いる場合は、きょうだいを離さずに一緒に養育できるかどうか」という判断基準です。
両親の離婚によってどちらかの親と離れてしまうだけでなく、きょうだいとまで離されてしまうと、お子様の心に大きなショックを与えると考えられています。そのため、きょうだいを一緒に育てられる環境が整っていることが重要視されます。
6. 面会交流への前向きな姿勢
お子様と離れて暮らす親との「面会交流」を認めることができるかという点も、親権を得るための重要なポイントの一つです。「面会交流」はお子様の権利です。
たとえ離婚相手のことが嫌いだったり、心理的に受け付けられなかったりしても、お子様にとっては大切な親であることを忘れずに、面会交流は認めるようにしましょう。
なお、お子様に対して虐待やDVがあった場合は、面会交流を認めなくても不利にはなりません。あくまでも、お子様の利益を最優先していることをアピールすることを忘れないようにしましょう。
7. お子様との心理的な結びつきの強さ
親権争いで「母親が有利」と言われる理由の一つに、「母性優先の原則」という考え方がありました。これは、特に乳幼児の親権者には「母性を有するものが望ましい」とする考え方です。日本では基本的に「母性を有するもの」は母親であると判断されることが多く、母親が親権争いでは有利とされてきました。
しかし、近年では共働き家庭が増えたことで、父親もお子様の世話をするケースが増えてきました。そのため、「お子様との心理的な結びつきの強い方を親権者とするべき」だという考え方に変化してきています。
したがって、「母親があまり育児をしていない」「母親が仕事に専念している」といった場合は、父親でも親権を獲得できる可能性が高まっています。
かがりび綜合法律事務所では、大阪を中心に多くの離婚問題を解決に導いてきました。親権問題でお困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。親身になってサポートさせていただきます。
お客様(感謝)の声
かがりび綜合法律事務所です!
お客様(感謝)の声をご紹介いたします!これからもこのようなお声をいただけるよう一層精進してまいりたいと思います!
★お客様(感謝)の声
数年前にモラハラDV夫との離婚時、公正証書の作成も含めて大変お世話になりました。初めの無料相談で弁護士事務所を数ヶ所訪れ「そんな相手なら養育費は諦めるしかない」と有り得ない事を言う弁護士もいた中、野条先生はとても親身に相談に乗ってくださり、ど素人の初歩的な質問の数々にも丁寧かつ端的にご説明いただき、基本的に話の通じない相手との連絡も粛々と進めてくださいました。
相手と直接顔を合わせないといけない場面でも事前に「もし話しかけられても無視でいいですよ」「顔も見る必要ないです」等とお気遣いくださり、終わった後に相手に尾行されるのが怖いと話すとわざわざ時間をおいて駅までお見送りしてくださったりもしました。
これで一件落着かと思いきや最近養育費の件で相手と揉め出し、公正証書の養育費増額調停の件で再度お世話になりました。相談内容をお話する中で前回の詳細を思い出されたご様子で、心底申し訳なく思いながらも他の先生に一からご説明する気力もなく再びお力を借りる形となりました。この度も相手方との連絡を全て請け負ってくださり、無事1回の調停で落とし所をつける事ができました。非常に信頼できるお仕事をされる中でも「良いお年を、と言えなくなる事態にならなくて良かったです」等とこちらの緊張や疲労を和らげてくださるお言葉をいただいたり、私の何百倍も御尽力いただいたにも関わらず相談者の悩みに常に寄り添ってくださり、事務所にご訪問した際マスクをしていたにも関わらず離婚時よりも痩せている事にまで気づいてくださったり(こちらが言い出すまでご指摘されませんでした)と細やかな気配りや記憶力にも大変感動いたしました。初めての調停が不安すぎて頼りにさせていただきましたが、協議離婚、調停対応と大変勉強になりました(勿論そんな勉強要らない人生の方がいいんですけどね。笑)。 モラハラ以外にも幅広い分野にお強い先生のようですが、どんな悩みにも真摯にご対応くださいますのでもしご自身や周りにお困りの方がおられましたら是非一度こちらの事務所様にご相談される事を強くお薦めいたします。
弁護士法人かがりび綜合法律事務所
この度は本当にありがとうございます!かがりび総合法律事務所の弁護士の評価いただきまして心から光栄に思うと共に身の引き締まる想いです!これからもより依頼者、そして社会に貢献できる法律事務所を目指してまいりたいと思います!
離婚や不倫などの男女問題のほかに、債務整理、相続、交通事故部門もございます。何かお困りごとがありましたらおっしゃってくださいますようお願いします。
離婚でのペアローン問題には以下の点に気をつける必要があります。
離婚でのペアローン問題には以下の点に気をつける必要があります。 1. **責任分担の明確化**: 離婚に伴い、ペアローンの返済責任をどのように分担するのか、明確に決めることが重要です。これに関する合意書を作成し、裁判所に提出することも検討されます。 2. **早急な対応**: ペアローンは夫婦共同で契約を結んだものであり、一方の配偶者が借主として責任を負っています。離婚後は、遅延や滞納が起きる可能性があるため、迅速な対応が求められます。 3. **返済方法の再検討**: 離婚に伴い、収入や家計が変化する可能性があります。ペアローンの返済方法や金額について、再検討が必要です。 4. **解約の検討**: 離婚後、ペアローンの解約を検討する場合もあります。解約には手数料や違約金がかかることがありますので、注意が必要です。 5. **金融機関との連絡**: 離婚後のペアローンに関する問題や変更点について、金融機関と適切に連絡や説明を行うことが重要です。 ペアローンの問題は、離婚手続きにおける重要な要素の一つです。専門家や弁護士の助言を仰ぎながら、適切な対応を行うことが重要です。
間接的面会交流
こんにちは! かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です! 本日は、面会交流について葛藤なされている方に向けて、間接的な面会交流の裁判例をご紹介していきます。 さて、面会交流について監護親の方が強く葛藤されている方も多いのではないでしょうか。それもそのはずで、元々信頼関係が構築されていないことが多いのが現状です。このような場合に果たして直ちに直接的な面会交流を認めるべきなのでしょうか? 間接的交流に関する裁判例では、以下のようなものがあります! さいたま家審平成 19・7・19 家月 60 巻 2 号 149 頁16 これは離婚後、子が非親 権者である父との面会交流を希望しているとして、親権者である母から面会交流の申立てがなされた 審判例として注目されたものです。 母からの申立ての内容は月 1 回の直接的面会交流であり、裁判所も、子が父に対して手紙を送付したり電話を掛けたり(留守番電話へのメッセージの吹き込み)し ており、その文面からしても相手方に会いたいと考えていることが認められるとしました。 しかしながら、、子が 離婚時には 2 歳になったばかり(審判時は小学校 4 年生)で、抽象的な父親像をもつに留まると推察されること、また、父母の離婚から 6 年以上が経つが、離婚に至るまでの父母の葛藤は極めて根深か ったこと、さらに、父が再婚家庭を築いていることも考慮し、「直接の面接交渉を早急に実施すること は、未成年者の福祉に必ずしも合致するものではなく、消極的にならざるを得ないとし、将来的には、環 境を整えて、面接交渉の円滑な実施が実現できるようになることが期待されるが、当分の間は、間接 的に、手紙のやり取りを通じて交流を図ることとするのが相当である」と判示しました。 【8】名古屋高裁平成 26・4・10(平成 25 年(ラ)第 469 号)は、別居中の母が、子 3 名(年齢は 不明)との面会交流を求めた事案であり、原審は直接的面会交流を認めず、手紙や電話、メールのや り取りによる間接的交流のみを認めたため19、母が即時抗告した。抗告審では、原審判を取り消し、「面 会交流に対する未成年者らの拒否的ないし消極的態度があることは否定できないことや、未成年者ら が抗告人と遠距離の地に居住していることに加え、未成年者らの年齢、生活状況及び当事者の意見等 を併せ考慮すると、春休み、5 月の連休、夏休み及び冬休みに各 1 回の面会を実施するとともに、自由な間接的交流を行うのが相当である」としました。具体的な面会交流要領では、直接的面会交流は各回 3 時間であり、間接的交流については「相手方は、抗告人と未成年者らが互いに手紙、電話、電子メ ールにより連絡すること及び抗告人が未成年者らにプレゼントを送付することを妨げてはならない」 とされています。
面会交流の履行勧告を受けた場合、以下の点に気をつけることが重要です。
面会交流の履行勧告を受けた場合、以下の点に気をつけることが重要です。 1. **履行の意思**: 面会交流の履行勧告がある場合、まずは履行する意思を示すことが重要です。子供との関係を大切にし、面会の機会を守ることが子供の利益につながります。 2. **日程や時間の確認**: 履行勧告に基づいて、面会交流の日程や時間を確認し、正確に履行することが求められます。遅刻や欠席は避けるよう努めましょう。 3. **コミュニケーション**: 子供との面会交流を大切にするため、コミュニケーションを円滑にすることが重要です。子供との楽しい時間を過ごすことを心がけましょう。 4. **記録の取り方**: 面会交流の履行に関する記録を適切に取ることが重要です。面会の日時や内容、子供の様子などを記録しておくことで、後日の証拠となる場合があります。 5. **相手との協力**: 面会交流の履行において、元配偶者との協力が求められる場合があります。協議や調整が必要な場合は円滑に進めるよう努めましょう。 面会交流の履行勧告は、子供との関係を保つために重要な手段です。子供の利益を最優先に考え、履行勧告に従いつつ、円滑な面会交流を実現する努力を心がけることが重要です。
親権獲得における判断要素
夫婦の間に子どもがいるときだけは、どちらかが親権者にならない限り離婚することはできません。
裁判で親権を決定する場合、どちらを親権者としたほうが子どもの利益になるかを第一に考えます。
具体的には、以下の点が判断材料となり総合的に判断されます。
- 子どもの監督状況
- 親権者の経済力
- 代わりに面倒を見てくれる人の有無
- 親権者の年齢や健康状態
- 住宅事情や学校関係などの生活環境
- 子どもの人数、それぞれの年齢や性別、発育状況
- 環境の変化による子どもへの影響度合いの見込み
- 子どもが10歳ごろ以上の場合、本人の意思
一般的に、子どもが幼いほど母親が親権者になる傾向にありますので、妻が離婚時に子どもの親権が欲しい場合は特に大きな問題はないと考えてよいでしょう。お困りの方はかがりび綜合法律事務所の無料相談制度をご利用ください!
間接的な面会交流の裁判例
こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
本日は、面会交流について葛藤なされている方に向けて、間接的な面会交流の裁判例をご紹介していきます。
さて、面会交流について監護親の方が強く葛藤されている方も多いのではないでしょうか。それもそのはずで、元々信頼関係が構築されていないことが多いのが現状です。このような場合に果たして直ちに直接的な面会交流を認めるべきなのでしょうか?
間接的交流に関する裁判例では、以下のようなものがあります!
さいたま家審平成 19・7・19 家月 60 巻 2 号 149 頁16
これは離婚後、子が非親 権者である父との面会交流を希望しているとして、親権者である母から面会交流の申立てがなされた 審判例として注目されたものです。
母からの申立ての内容は月 1 回の直接的面会交流であり、裁判所も、子が父に対して手紙を送付したり電話を掛けたり(留守番電話へのメッセージの吹き込み)し ており、その文面からしても相手方に会いたいと考えていることが認められるとしました。
しかしながら、、子が 離婚時には 2 歳になったばかり(審判時は小学校 4 年生)で、抽象的な父親像をもつに留まると推察されること、また、父母の離婚から 6 年以上が経つが、離婚に至るまでの父母の葛藤は極めて根深か ったこと、さらに、父が再婚家庭を築いていることも考慮し、「直接の面接交渉を早急に実施すること は、未成年者の福祉に必ずしも合致するものではなく、消極的にならざるを得ないとし、将来的には、環 境を整えて、面接交渉の円滑な実施が実現できるようになることが期待されるが、当分の間は、間接 的に、手紙のやり取りを通じて交流を図ることとするのが相当である」と判示しました。
名古屋高裁平成 26・4・10(平成 25 年(ラ)第 469 号)は、別居中の母が、子 3 名(年齢は 不明)との面会交流を求めた事案であり、原審は直接的面会交流を認めず、手紙や電話、メールのや り取りによる間接的交流のみを認めたため19、母が即時抗告した。抗告審では、原審判を取り消し、「面 会交流に対する未成年者らの拒否的ないし消極的態度があることは否定できないことや、未成年者ら が抗告人と遠距離の地に居住していることに加え、未成年者らの年齢、生活状況及び当事者の意見等 を併せ考慮すると、春休み、5 月の連休、夏休み及び冬休みに各 1 回の面会を実施するとともに、自由な間接的交流を行うのが相当である」としました。具体的な面会交流要領では、直接的面会交流は各回 3 時間であり、間接的交流については「相手方は、抗告人と未成年者らが互いに手紙、電話、電子メ ールにより連絡すること及び抗告人が未成年者らにプレゼントを送付することを妨げてはならない」 とされています。
どうして家庭裁判所の調査官が調査するのか?
こんにちは! かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です。 さて、本日は、どうして家庭裁判所の調査官が調査するのか、です!!特親権や面会交流のことで悩まれている方が多い印象です。調査官とどう接していいか、ということもありますが、そのあたりは是非ご相談いただきたいと思っています。 まず、当事者やその置かれている人間関係や環境に適応させるために、当事者やその家族らに与える助言援助、情緒の混乱や葛備の著しい当事者に対して情緒の緊張を緩和し、感情の葛藤を鎮め、自己洞察力を回復させて理性的な状態で手続に関与できるようにしていく必要があります。 家事事件、とりわけ離婚事件は、今後の人間関係について、手続の下で対立する当事者間の争訟を裁断することを目的とする考えとは相容れないとの考えに基づいています。 例えば、面会交流にたとえてみます。裁判官が面会交流を認めます。と言ったとしても、その回数や方法、内容、手段を具体的どういう風にやっていきましょうという内容がなければ全然進みません、絵に描いた餅です。 家裁調査官の事実の調査は、実際に調査事項及び調査の具体的内容は、当事者の求めによって決めるのではなく、裁判所の必要に基づいて定められます。 調査事項としては、子の監薄状況、子の意向又は親権者としての適格性とされる場合が大部分でありますが、裁判所は、審理の経過、証拠調一慮して必定めていき、子の監護状況及び非監護親の監護態勢監護親が現にしている子の監護状況を確認し、それが子の福祉に適っているとされ、事案に応じて、監護親の面接調査、監護補助者の面接調査、監護親宅への訪問調査及び子が在籍する学校、保育所等の調査などの監護親側の調査が行われます。なお、親権の判断に必要な場合には、監護親側の調査に加え、非監護親側の監護体制の調査が行われる場合もあり、具体的には、事案に応じて、非監愛親の面接調査、監護補助予定者の面接調査及び非監護親宅への訪問調査などが行われるます。 「大阪家裁における人事訴訟事件の事実の調査の実情について」家裁調査官研究紀要6号(2007)161頁に、具体的な調査事例の類型化が記載されています。 このように家庭裁判所の調査官の内容は意外と奥深くここをどのように当事者として接していくか重要です。だからこそ寄り添う代理人が必要になりますのでお困りの方、これから親権や面会交流のことでお悩みの方はご相談ください。宜しくお願いします。
面会交流のルール作りの重要性
こんにちは!
かがりび綜合法律事務所代表弁護士の野条です!
面会交流について悩まれている方は実は多いのです。面会交流のルールは守らなければならないことから、ルール作りはだからこそ慎重になければならないですね!面会交流の作戦は結構深いんです…
面会交流については法務省のページで次のように言われています!
面会交流に応じなければならないのですか。
(A)
面会交流は,子どものためのものであり,面会交流の取り決めをする際には,子どもの気持ち,日常生活のスケジュール,生活リズムを尊重するなど,子どもの利益を最も優先して考慮しなければなりません。
面会交流を円滑に行い,子どもがどちらの親からも愛されていることを実感し,それぞれと温かく,信頼できる親子関係を築いていくためには,父母それぞれの理解と協力が必要です。夫婦としては離婚(別居)することになったとしても,子どもにとっては,どちらも,かけがえのない父であり母であることに変わりはありませんから,夫と妻という関係から子どもの父と母という立場に気持ちを切り替え,親として子どものために協力していくことが必要です。
なお,相手から身体的・精神的暴力等の被害を受けるおそれがあるなど,面会交流をすることが子どもの最善の利益に反する場合には,以上の点は当てはまりません。
離婚前での面会交流にお困りの方はかがりび綜合法律事務所までご相談ください。