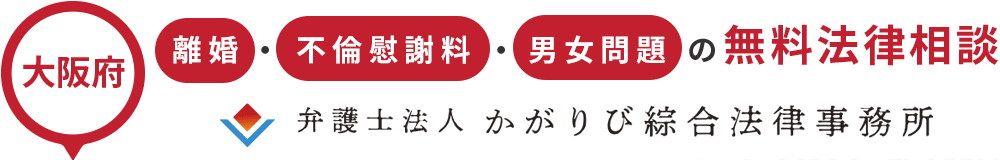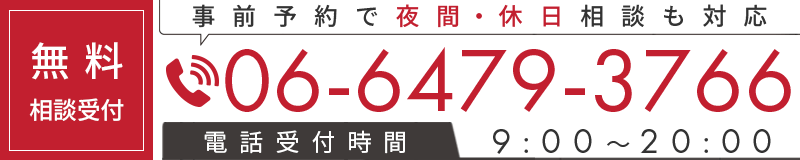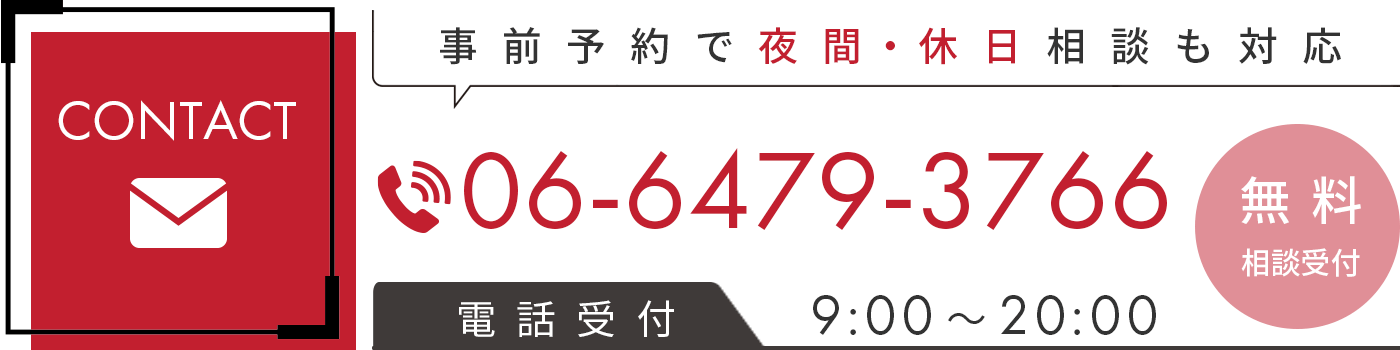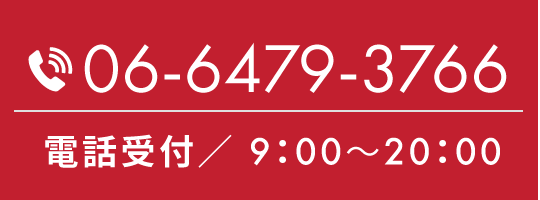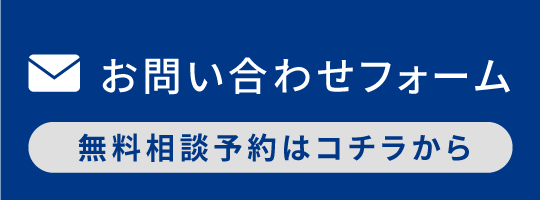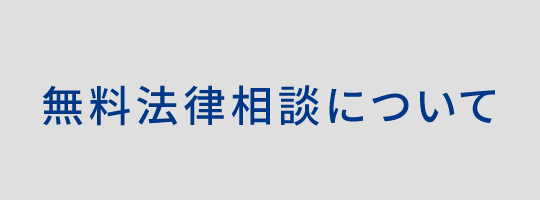このページの目次
【離婚弁護士が徹底解説】退職金・企業年金は財産分与の対象?計算方法から注意点まで
皆さん、こんにちは。弁護士法人かがりび綜合法律事務所の離婚弁護士、野条健人です。
「夫(妻)がもうすぐ定年退職だけど、退職金って離婚してもらえるの?」 「企業年金も財産分与の対象になるって本当?」 「将来もらえるはずの退職金、どうやって計算すればいいの?」
もしあなたが今、このようなお悩みを抱えているなら、このブログ記事はきっとお役に立てるはずです。
離婚における財産分与は、夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた財産を公平に分ける手続きです。預貯金や不動産はイメージしやすいですが、退職金や企業年金といった「将来受け取るお金」や「形のない財産」が財産分与の対象になるのかどうかは、多くの方が疑問に感じる点です。
私はこれまで、多くの離婚案件に携わり、特に退職金や企業年金といった複雑な財産分与の問題を数多く解決に導いてきました。このブログ記事では、退職金・企業年金が財産分与の対象となる条件、具体的な計算方法、そしてあなたが損をしないための注意点まで、専門家として分かりやすく、徹底的に解説していきます。
1.退職金・企業年金は財産分与の対象になる?基本原則を解説
結論から言うと、退職金や企業年金は、原則として財産分与の対象となります。
これは、退職金や企業年金が、婚姻期間中の夫婦の協力によって形成された「賃金の後払い的性格」を持つと考えられるためです。夫婦の一方が働いて退職金や年金を受け取る権利を得たのは、もう一方の家事や育児、内助の功があってこそ、と法的に評価されるのです。
ただし、全ての退職金や企業年金がそのまま対象になるわけではありません。重要なのは、以下のポイントです。
- 婚姻期間中の貢献度: 財産分与の対象となるのは、夫婦が協力して財産を築いた婚姻期間に対応する部分のみです。
- 財産的価値の確定: 将来受け取る退職金の場合、現時点での財産的価値をどのように評価するかが問題になります。
2.退職金・企業年金の財産分与、どんな場合に認められる?
退職金・企業年金が財産分与の対象となる具体的なケースは、大きく分けて以下の2つです。
(1) すでに退職金・企業年金が支払われた場合
すでに退職金や企業年金が支払われ、それが預貯金として残っている場合、または他の財産に形を変えている場合です。この場合は、現にある財産として財産分与の対象となり、夫婦の共有財産に含めて計算します。
(2) 将来退職金・企業年金を受け取る予定がある場合
これが最も複雑なケースです。まだ退職金を受け取っていない、あるいは退職が先の場合でも、その権利が成熟していれば財産分与の対象となります。
- 定年退職が間近な場合: 会社に退職金規定があり、定年退職が間近に迫っている場合など、退職金が支払われる蓋然性が高い場合は、財産分与の対象となりやすいです。
- すでに退職金規程がある場合: 会社の退職金規程に基づき、現在自己都合退職した場合に支給される退職金相当額を基準に計算することもあります。
- 企業年金の場合: 企業型確定拠出年金(DC)や確定給付企業年金(DB)など、様々な形態がありますが、これも原則として財産分与の対象となります。特に、婚姻期間中に積み立てられた部分が対象です。
【実務上の取り扱い】 実務では、数年後に退職が予定されており、その時点での退職給付金額がある程度判明している場合に限り、財産分与の対象財産として、その額を現在の価値に引き直して計算することが多いです。 一方で、10年後、20年後といった遠い将来の退職金については、受け取れるかどうかの不確実性が高いため、財産分与の対象とはしない、または認められにくい傾向にあります。これは、将来の経済状況の変化や退職金制度の改定、自己都合退職など、予測が困難な要素が多いためです。
3.退職金・企業年金の財産分与の計算方法
退職金・企業年金を財産分与の対象とする場合、その計算方法にはいくつかの考え方があります。
最も一般的な計算式は以下の通りです。
財産分与の対象額 = 退職金総額 × (婚姻期間/勤続期間)
ただし、これは簡略化した計算式であり、実際には様々な要素が考慮されます。
- 退職金総額:
- すでに支給されている場合: その金額が基準となります。
- 将来支給予定の場合: 勤務先の退職金規定に基づき、「現在自己都合退職した場合の支給額」や、「定年まで勤務した場合の予想支給額」などを基に算出します。この際、将来の退職金はインフレや会社の業績によって変動する可能性があるため、「中間利息控除」(ライプニッツ係数などを用いて現在の価値に換算)を行うことがあります。
- 婚姻期間: 夫婦が婚姻していた期間(同居期間)です。
- 勤続期間: 退職金算定の基礎となる、会社に勤務した全期間です。
【企業年金の場合】 企業年金も同様に、婚姻期間中の掛け金や積立額、将来受け取る年金額などを考慮して計算されます。企業年金の種類によって計算方法が異なるため、専門的な知識が必要です。
【具体的な計算例】 例えば、夫が10年間勤務し、そのうち婚姻期間が7年間であった場合、退職金が200万円であれば、 対象額 = 200万円 × (7年/10年) = 140万円 となり、この140万円の2分の1が妻の取り分となる、という考え方です。 ただし、これはあくまで一例であり、個別の事情によって複雑な計算や調整が必要になります。
4.退職金・企業年金に関する財産分与の注意点とトラブル事例
退職金・企業年金の財産分与は、以下のような注意点やトラブルが生じやすい分野です。
(1) 資料収集の困難さ
退職金や企業年金の正確な情報を得るには、勤務先からの資料(退職金規定、退職金試算表、年金規約、積立状況など)が必要となります。しかし、相手方が協力的でない場合、これらの資料を入手することが難しいケースがあります。弁護士であれば、弁護士会照会制度などを利用して、会社に資料の開示を求めることが可能です。
(2) 将来の不確実性
「将来、会社が倒産したら退職金が支払われないのでは?」「途中で転職したらどうなるの?」といった不確実性があるため、裁判所が財産分与の対象としない、あるいは金額を減額する判断をすることもあります。
(3) 定年退職後の合意の有効性
退職金が支払われた後に、その財産分与について別途合意することも可能です。例えば、「退職金が出たら清算金を支払う」という合意も有効です。この場合、「退職後、2ヶ月以内」など、具体的な支払時期を明確に定めておくことが重要です。
(4) 退職金を受け取った側の主張
退職金を受け取る側が、「これは婚姻期間中の貢献とは関係ない」「全額は渡せない」と主張してくることがあります。特に、リストラによる退職金や、特定の功績に対する報奨金のような性格を持つ退職金の場合、争点となることがあります。
5.退職金・企業年金の財産分与は弁護士にご相談を!
退職金や企業年金の財産分与は、その性質上、非常に複雑で専門的な知識を要します。
- 対象となるかどうかの判断: 個別のケースで財産分与の対象となるか否か。
- 正確な金額の算定: 複雑な計算方法や、将来の価値の評価。
- 資料収集の困難さ: 相手方が非協力的な場合の資料確保。
- 交渉の専門性: 退職金を受け取る側の抵抗も予想されるため、説得力のある交渉。
これらを個人で対応しようとすると、時間も労力もかかり、結果的に損をしてしまうリスクが高まります。弁護士に依頼することで、あなたの権利を最大限に守り、適切な金額での合意を目指すことができます。
弁護士法人かがりび綜合法律事務所では、退職金・企業年金を含む財産分与に関する初回のご相談を無料で承っております。
あなたの状況を丁寧に伺い、最適な解決策をご提案させていただきます。私、野条健人が、あなたが納得のいく形で問題を解決し、安心して未来へ進めるよう、全力でサポートいたします。
どんな些細なことでも構いません。まずはお気軽にご連絡ください。
弁護士法人かがりび綜合法律事務所 離婚弁護士 野条健人
【お電話でのお問い合わせ】 電話: 06-6479-3766 FAX: 06-6479-3767